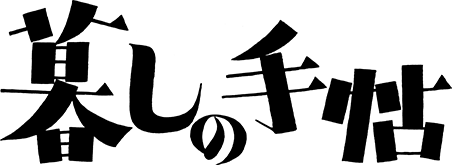反復横跳び、ときどき休憩
第5回 ほんとうの時間
2025年08月13日

間違いなく、時間の流れがいつもより遅くなっていたことがある。なんだか倦怠感があり、頭がぼーっとして、やる気がなかなか出なかった朝のこと。疲れているのかもしれない、少し仮眠でもとったらマシになるかもと、横になって目を閉じてみる。目を閉じている間も思考はぐるぐるとわたしのなかを駆け巡っていて、なんだか苦しい。しばらくそうやって過ごして、10分くらい経ったかな、と時計を見ると、なんと2分しか経っていなかった。あれ。これは明らかにおかしい。もしかして……と体温計を取り出し熱を測ってみたところ、わたしの体温は38度を超えていた。すぐさま解熱剤を飲んで布団に潜り込み、いつもと違う頭の感覚に翻弄されながらも、内心、なにこれ、すごい! と驚いていた。時間感覚の違和感から、自分の体調の異変に気づいたのは、初めてだった。
「好きな人といると1時間が1分のように感じられ、熱いストーブの上に手を置くと、1分が1時間に思える。それが相対性というものだ」。そんな話を、アインシュタインが例えに使ったらしい。この日わたしが感じた“時間ののろさ”も、たしかにそれと似ていた。たしかに、時間というのは絶対的なものではなく、状況や心身の状態によってぐんと伸びたり、ぎゅっと縮んだりする。
時間について考えるときによく思い出すのは、高校3年時の担任の先生が話してくれたことだ。たしか、ホームルームの時間だったと思う。先生はこう言った。「時間は、年齢を重ねるほど早く感じるようになる。君たち18歳は、体感時間の折り返し地点にいる」と。それは冬の時期で、卒業まであと数カ月の頃だった。輝かしい未来に胸を躍らせるわたしたちに先生はなんてむごいことを言うんだろう、一生なんてあっという間だぜ、ってこと? と、制服を着たわたしはその言葉を余命宣告のように受け取ってしまった。けれど、その時間感覚の不思議さについては、強く納得もしていた。小学1年生のころは、アニメの『名探偵コナン』の放送日までが、果てしなく遠く感じられた。でも、高校3年生のわたしにとっての一週間は、そこまでのろくない。これから先、もっともっと時間が早く感じられるなんて、恐ろしいことだ、と本気で思った。
実際、それからの時間はどんどん加速していった。社会人になってからの1週間なんて、瞬きのように過ぎていく。新卒で勤めていた制作プロダクションは、洞窟のような形状の建物で、内装は窓を塞ぐように作られていた(実際、建物の名前に洞窟を意味する「cave」がついていた)。出社して仕事に没頭していると、気づいたときにはどっぷりと夜になっていて、あれこれしているうちにすぐ終電の時間になった。深夜に自宅に帰って、泥のように眠って、翌朝また会社へ行く。季節を感じる余裕なんてないくらい、あっという間に毎日が過ぎていった。かつて『名探偵コナン』を待ちわびたのと同じ“7日間”だとは、到底思えなかった。
でも、ここ数年、わたしの時間は、逆に異様に“濃い”。
歌人・作家として活動をはじめてから、時間の密度がそれまでの何倍にもなったように感じている。たとえば第一歌集『水上バス浅草行き』は2022年刊行、第二歌集『あかるい花束』は昨年・2024年に出たばかりなのに、『あかるい花束』からは3~4年は経ったような気がするし、第一歌集に関しては、9年くらい昔のことのように思えてしまうのだ。
そう感じてしまう理由として、心当たりが二つある。
一つは、出版後、自分にとって新しい経験ばかりが続いていること。たとえば、自分の名前が書かれた書籍が書店に並んだり、エッセイの連載が始まったり、ラジオに出演したり、サイン会で読者と直接話したり。日々、初めてのことに向き合っている。緊張したり、嬉しくなったり。そのたびに、心の振り子が大きく揺れる。
もう一つは、二拠点生活をしていること。
居場所が変わると、そのたびに「新しい朝」が始まる気がする。景色が切り替わるたび、擬似的に1日をもう一度やり直しているような感覚になる。同じ時間に起きて、同じ電車に乗り、同じ場所へ帰る生活では味わえなかったリズムがある。
ちなみに、体感時間が延びている瞬間はいくつかあるらしい。たとえば、代謝が上がっているとき。細かいことに注目して、たくさんのことに気づいているとき。新しい経験をしているとき。どれも、作家としての生活を送るようになってからの自分に当てはまることばかりだ。
わたしの好きな映画に『インセプション』という作品がある。夢の中へ潜り、他人の意識にアイデアを植え付けるという物語だ。夢には複数の層があり、深く潜れば潜るほど、時間の流れがゆるやかになる。最下層には「虚無」と呼ばれる場所があり、主人公はそこで約50年過ごしたことがある。もっと長く一緒にいたい2人が、現実から離れて、自分たちだけの街を夢の中につくる――その甘美で、恐ろしくて、あまりに生々しい願いと過ちの描写が好きだ。
けれど、今のわたしの1年が「3年ぶん」に感じられるほどなら、夢の最下層で過ごす何十年は、どれほどの重さなのだろう。自分が感じている時間の伸び縮みと彼らの虚無での時間の流れ方を比べようとして、途端に怖くなった。
そして、ふと思う。これまでよりも体感時間が緩やかになったわたしの現実は、本当に現実なのだろうか。もしかして、これも夢のどこかの階層の時間なのだろうか。
いつか、目が覚めてしまうのかもしれない。そのとき、わたしはどこにいて、「ほんとうの現実」は、どんな姿をしているのだろう。
文 岡本真帆
岡本真帆(おかもとまほ)
歌人、作家。1989年生まれ。高知県出身。SNSに投稿した短歌「ほんとうにあたしでいいの?ずぼらだし、傘もこんなにたくさんあるし」が話題となり、2022年に第一歌集『水上バス浅草行き』を刊行。ほかの著書に『あかるい花束』『落雷と祝福 「好き」に生かされる短歌とエッセイ』。東京と高知の二拠点生活、会社員と歌人の兼業生活を送るなかで気づいた日々のあれこれを綴る。