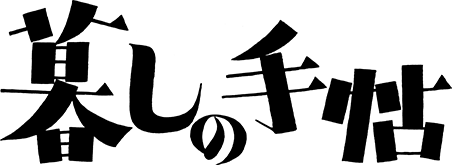日本文学を訳すモノです
第10回 芸人と翻訳者のトークイベント
2026年02月18日

先月、少し現実味のない出来事があった。
なんと私、芸人で作家でもあるヒコロヒーさんと、ソウルの中心でトークイベントを行ったのである。これまで私のエッセイや、拙著『面倒だけど、幸せになってみようか』を読んでくださった方ならご存じだと思うが、私は生まれつきの恥ずかしがり屋だ。人前で話すのは、この世でいちばん苦手なことだった。人の視線が集まるだけで、頭の中は真っ白になってしまう。そんな私が、あのヒコロヒーさんと、である。
前回触れたヒコロヒーさんの小説『黙って喋って』が、このたび韓国で出版された。それに際してご本人が来韓され、トークイベントが開かれたのだ。私はその翻訳者として参加し、あろうことか司会役まで務めることになった。
本来なら、そんな大役を前にして、逃げ出したくなるほど震え上がっていたはずなのだが、実を言うと、このときの私には「意外とうまくできるかも」という、根拠のある自信があった。
というのも、その前の週に県内の小学校教員研修会に招かれ、子どもの本の翻訳について3時間にわたる講演を行い、意外にも「とても新鮮で面白かった」と好評をいただいたからである。
その結果、「私って、けっこうスピーチの才能があるのでは」と、見事に調子に乗ってしまったのだ。浮かれた気分のまま、会場へ向かった。
ところが、テレビで見るそのままの、背が高く、ウェーブのかかったロングヘアに、お肌がきれいで、圧倒的なカリスマ性を放つヒコロヒーさんが隣に座った瞬間、その勢いは一瞬で吹き飛んだ。心臓は狂ったように高鳴り、手首のスマートウォッチが、ひっきりなしに心拍数の異常を振動で知らせてくる。もう、分かっているから黙って。
私はどうにか口を開き、冒頭のあいさつをこう切り出した。
「翻訳という私の仕事は、まるで無言の行を続ける修行僧のようなものです。ほとんど言葉を発しません。その仕事を始めて、今年で35年目になります。一方で、作家のヒコロヒーさんは本業が芸人で、日本で今もっともホットな話し手として活躍されています。そんな35年目の黙行修行者と、売れっ子の話し手が、トークイベントを開催することになりました。しかも、しゃべれない私が司会を担当します。これって、どこにもない空前絶後のコメディーじゃないですか。今の私の気分を例えるなら、クリーニング店の前で、通販のスチームアイロンをかけているような心地です」
心臓と一緒に、声までガタガタと震えていた。「30分もすれば、横になって聞きたくなるほど落ち着くはずです」と断りを入れた。時間が経つにつれて震えは収まったが、韓国語と日本語、二つの言葉が飛び交う中で、脳がついていくのに必死だった。
なんとかイベントは終わった。
だが、その後の1週間というもの、反省点ばかりが脳内でリプレイされ続けた。
「あの質問は、あまりに取るに足らないものだった」
「あの一言は、言わなきゃよかった」
考え始めるときりがなく、気付けば同じところを何度も堂々巡りしていた。
たった1カ所の誤訳に何年もさいなまれるほど、翻訳者というのは往々にして執念深い生き物なのだ。
やはり私は、スピーチ向きの人間ではないらしい、と思った。
それから再び本業に戻り、若竹千佐子さんのエッセイ『台所で考えた』のゲラに目を通した。若竹さんは、63歳で『おらおらでひとりいぐも』を書き上げ、芥川賞を受賞された作家である。翻訳している最中には何気なく通り過ぎていた一文が、鮮やかに目に飛び込んできた。
「藤井聡太くんが将棋の新人としてデビューした頃、私も新人と言われていたのが自慢です。新人にして老人。」
ああ、そうだ。司会という役割において、あの日、私は紛れもなく青臭い「新人」だったのだ。35年間、翻訳という名の「黙行」を続けてきた私が、いきなり人前で、あまつさえ「うまくやろう」などと考える方が、どこか滑稽だったのかもしれない。
初めての司会は、危うく「デビュー戦」がそのまま「引退試合」になるところだった。 けれど、震えながらも自分の声を世に放ったこと自体、私にとっては確かに大きな一歩だった。いつかヒコロヒーさんのように、圧倒的なカリスマ性と光り輝くような話術で、会場を爆笑の渦に巻き込む日が来……いや、そんな日は一生来ないだろうけれど。
次にスピーチをするときには、せめてスマートウォッチが「心拍数異常」の振動を繰り返さない程度に、「新人なりの余裕」を見せたいものである。 (——って、あんた、またやるつもり?)
若竹千佐子さんの『台所で考えた』は、韓国では『人生の午後にも祭りは起きる』というタイトルで刊行される。来月、還暦を迎える私の人生の午後、どうやら祭りは始まったようだ。
文 クォン・ナミ
クォン・ナミ
韓国を代表する日本文学の翻訳家。エッセイスト。1966年生まれ。20代中頃から翻訳の仕事を始め、30年間に300冊以上の作品を担当。数多くの日本作家の作品を翻訳し、なかでも村上春樹のエッセイ、小川糸、益田ミリの作品は韓国で最も多く訳した。著書に『スターバックス日記』『面倒だけど、幸せになってみようか』など。日本語版が刊行されているものに『ひとりだから楽しい仕事』『翻訳に生きて死んで』がある。