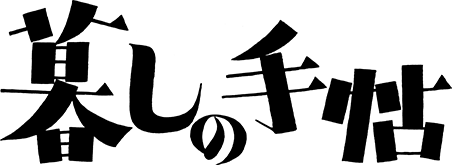反復横跳び、ときどき休憩
第8回 内なる批評家を黙らせる
2025年11月12日

最近は、歌人や作家としての活動を通して知っていただく機会が多いからか、「会社員です」と話すと驚かれることがある。とっくに専業作家になったのだと思った、と言われるが、兼業作家として週5日元気に働いている。コロナ禍に始まったフルリモート勤務はつい先日終わりを迎え、今では週に3日、渋谷のオフィスに出社するような生活をしている。引き続き高知にも拠点を持ちつつも、この先は東京の自宅にいることの方が多くなりそうだ。
会社の勤務時間は、10時から19時まで。私は始業前の2〜3時間を、執筆などの仕事にあてている。
自分に文才がある、と思ったことはほとんどない。短歌を作る延長で、エッセイなどの散文も書くようになった。だからエッセイを書くのが得意だと思ったことはなく、むしろ最初は苦手意識があった。でも、何事も練習をすればそれなりにはなっていくもので、今はエッセイを書くときのお決まりの手順のようなものがある。
まず、なんとなく、このテーマで書こうと決めるところから始める。文章の真ん中にあるものを決定するイメージ、と言えばいいだろうか。たとえば「私の好きなお菓子」というテーマで書くと決めたら、それは具体的にはなんなのか、どうしてそれでなければいけないのか、他と比べてどうなのか、いつから好きになったのか……などなど、「私の好きなお菓子」に付随するあらゆる情報やエピソードを、まずはすべて書き出してみる。そうすると、その中で一番魅力的に書けそうなものや、具体的な文章の道筋が見えてくる。
頭の中にある要素を、いったんすべてテキストエディタやノートの上に並べることが大事だと思っている。そうすることで、不要な部分を削ったり、並び替えたり、さらに磨き上げることができるようになる。
もしかしたらこのやり方は、料理に似ているかもしれない。まず、今日はカレーを作ろう、と決めて、じゃあどんなカレーにしようかと具体的に考えていく。市販のカレールーを使った、家庭的なやつなのか。それともスパイスから作るカレーなのか。方針が決まったら、必要な材料を、すべて台所に並べてから、料理を開始する。
どんなカレーなのか、ちゃんと最初にイメージすること。文章も、その方がうまくいく。
もちろん作ってるうちにもっと良いものが思い付いたら、途中から変えてもいい。でも最初になんとなくのゴールを見据えていた方が、迷いがない。
書きたい文章の材料となるセンテンスがすべて並んだら、それをなめらかな文章の形に整えていく。頭から順に書いていく。ゴールまでの道筋がイメージしやすくなっている分、最初の材料洗い出しのタイミングよりもスムーズに書いていける気がする。
そのうちに初稿ができあがる。この初稿は表現にこだわったものというよりは、意味として成立している状態、読んで意味がわかるくらいの荒削りなものだ。あとは数回推敲をする。頭から読み直し、書き直す。客観的になるために紙に印刷したり、異なるエディタを使ってフォントやレイアウトを変えてみたり、PC画面だけでなくスマホで読んだり、iPadで読んだり、新鮮な気持ちで読み直せるように工夫している。数日空けると、書いたときの自分とは違う目線で文章を読み直せるので、余裕があるときは時間をかけて、文章を整える。
だいたいこんな風に私の執筆は進んでいく。
一つ、困りごとがある。それは、書いている最中、自分の中の別の人格が現れることだ。私はそいつのことを「内なる批評家」と呼んでいる。批評家は厄介で、書いている私の隣に立ち、腕組みをして、原稿を嘲笑しながらいろんなことを言ってくる。
「そんなの書いてどうするの?」「ぜんぜんおもしろくないよ」「才能ないのによく続けてるね」
うるさい。非常にうるさい。うるせ〜〜! と心の中で叫びながら、無視する。
私はずいぶん長い間、この内なる批評家の存在に頭を悩ませてきた。なぜなら実際、批評家が言っていることはもっともらしく聞こえる。これって本当に面白いんだろうか。このまま書いていて大丈夫なんだろうか。執筆中の私は、その批判的な声を真に受けて、不安になってしまう。自分の心の中にだけある批判の声に同調してしまう。そうなると、筆は止まり、書くことが憂鬱になってくる。SNSに逃避する。原稿は進まない。締切は近づいてくる。
この批評家くんは、ほぼ毎回、原稿を書き始めるとやってくる。そのたびに私は憂鬱な気持ちになっていた。書くの向いてないかも、とも思う。しかしあるとき、ふと気が付いた。
……批評家にしては、「出てくるタイミング」が早すぎるんじゃないか? と。
自分では何もせず、他人を批評するだけの人をあざけって批評家と呼ぶことがあるが、そうではなく、職業としての批評家について考えてみたい。批評とは、作品の価値を判断し、論じること。それを生業とするのが、批評家だ。
でも、待ってほしい。私が書いている文章はまだ推敲中のものだ。作品として完成していない。完成し、世に出たものならまだしも、内なる批評家は制作途中の作品に対してコメントしてくる。あんた、本当に批評家か? それって批評のルール違反なんじゃないの? そんな風に自称批評家を見つめると、奴はぐうの音も出ないのか、急にしおらしくなってしまう。作品が完成したら批評してもいい。いやむしろ、推敲に推敲を重ねて、これで世に出していいかな、と迷っているときにこそ、出てきてくれよ。そんな風に考えたら、私の中の批評家は敵ではなくなった。むしろ心強い味方になった。
内なる批評家を黙らせることはできない。だからうまく付き合っていきたい。あいつがいるのは、もっといいものを書きたい、文章をより良くしたい、という思いがあるからだ。批評の声もまた、私の一部。そう思えたとき、書くことがようやく楽になった。
今も書くたびに、やつは近くで腕組みをして待っている。でも、もう怖くはない。湯気の立つマグカップを横に置き、キーボードを叩く。「うるさいな」と心の中でつぶやきながら、今日も一行、書き進める。
文 岡本真帆
岡本真帆(おかもとまほ)
歌人、作家。1989年生まれ。高知県出身。SNSに投稿した短歌「ほんとうにあたしでいいの?ずぼらだし、傘もこんなにたくさんあるし」が話題となり、2022年に第一歌集『水上バス浅草行き』を刊行。ほかの著書に『あかるい花束』『落雷と祝福 「好き」に生かされる短歌とエッセイ』。東京と高知の二拠点生活、会社員と歌人の兼業生活を送るなかで気づいた日々のあれこれを綴る。