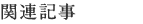『恐竜がいた』 下田昌克 絵・恐竜制作 谷川俊太郎 詩
スイッチ・パブリッシング 1,600円+税 装釘 船引奈々
下田昌克さんが作った恐竜を初めて目にしたのは、2014年春にパルコミュージアムで開かれていた「壱万円芸術 歪んだ大人展」でした。体育の授業で使う体操マットみたいなキャンバス地で、綿が詰められた、柔らかいような硬いような、1mくらいの大きさの恐竜の頭です。幾重にも刺された縫い目を見つめていると、太い針のついたミシンを無心に動かしている人、しかもその作業が楽しくてたまらない! という人の姿が頭に浮かんできて、作者はどんな方だろう、と気になっていました。
そして昨年、仲條正義さん(『暮しの手帖』の表紙を描いてくださっています)の個展「2016年、仲條」のオープニングで、下田さんのお姿を見つけ……。あれを縫い上げた人の手を、どうしても近くで見たい! と、どきどきしながら話しかけました。
「あるよ!」と、下田さんがおもむろにトートバッグから取り出してくれたのは、なんとその恐竜!! (……も、持ち歩いているの!?)「ぼくの恐竜に谷川俊太郎さんが詩をつけてくれてね。絵本にしたの」と、この本を紹介してくださいました。そのとき作品を被らせてもらったのですが、恐竜は想像より硬くて骨みたいで、一方で握手した下田さんの手は、うんとあたたかで柔らかい感じがしました。
下田さんは2011年夏、上野の国立科学博物館で「恐竜博」を見たことをきっかけに、遊びで恐竜の被り物を作り始めたのだそうです。
顎が「ガブーッ」と動いて、生命感に溢れる下田さんの恐竜。
いのちが生まれて消えるってどういうこと? と、恐竜にもう会えない、この世界の寂しさを綴る谷川さんの詩。
小さな骨や爪まで、地球に存在したはずの“かたち”を忠実に再現する下田さん。
「いのちのかたちをデザインしたのは いろんなかたちをきめたのは いったいなにか?」と、考える谷川さん。
ふたりの作品が、過去と現在、生と死の世界の間で、読む人の思索を引っ張り合って、ぐっと深いところへ連れて行ってくれます。
(長谷川)